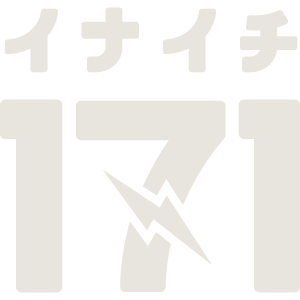2020.10.0517:14
飽き性 | アルバム制作にあたって
レコーディングはほぼ全てSTUDIO 246WESTと私の自宅。
アルバムに書き忘れたが、六甲道ハイダウェイも自己解決の歌録りに使った。
先程のPVの項では個人的な謝辞も書いたが、録音に使ったスタジオ、特に246WESTの皆さんへの感謝は計り知れない。
セルフレックのときも練習のときも、はたまた大学の部活時代から凄まじい量の迷惑をかけているし、様々なめんどくさいお願いにもいつも笑顔で対応して頂いた。
本当にありがとうございます。
ところで、生バンドのレコーディングをDIYする人間向けの情報というのは本当に落ちていないので、参考までに使用した機材を余すところなく書いてしまおうと思う。
ただし、「この機材でこのくらいの音は最低撮れるんだ~」という指標で見てほしい。
はっきり言って、SM57とMarshall 1960Aの組み合わせなら本来はもっといい音で録れる笑
間違っても、これらの機材の限界がこのアルバムだとは思わないでほしい。
ドラムは246の8スタに置いてあるやつと、PAISTEのチャイナ、チャドスミスモデルのスネア。
ドラムのマイキングはバスドラにオンマイクでSM57、オフでBETA52A、スネアはトップからSM57、エネルギーと煙と自己解決のみ裏からもSM57、タムもSM57、フロアタムはAudix D2、ライドとチャイナにSM57、ハイハットとLRトップに合計3本のAKG C391B。
ベースはレコーディング直前に3~4万で買ったYAMAHA SBVと、メインの音はJOYO DYNACOMPとJOYO SWEET BABY、ここぞというときにProco RAT2、アンプは基本246のHARTKE、マイキングは確かAKG D112とSM57、たまに57の代わりにSM58、全てアンプの表側からオンマイク。一応LINE出力の音も録ってはいたが、殆どミックスしていない。
ギターはP-90のGibson Les Paul StudioとたまーにメキシコのStratocaster、ジミヘンモデル。
メインの歪みはMarshall 1959か宅録時はBoss ST-2で、ちょっと上げたいときにFUZZ FACE MINIのジミヘンモデル、ここぞというときにBIG MUFF、懐古のキメとクラゲのラストのみBEHRINGER SF300。あとは所々にBOSSのVB-2wとTR-2とWHAMMY 5。
マイキングは246の1960AにSM57とSENNHEISER E609、半分くらいの曲はBETA52Aでも録っている。全て表側からオンマイク。
ボーカルは一部SM57やSM58が混ざっているが、ほぼ全てオーテックのAT4050(246のレンタル品 1回600円)、これ以外の上記のマイクは全て246WESTのセルフレコーディングサービスのデフォルト付属品(レコーディング当時)。あ、セルフレックルームのアイマックとFocusrite Scarlett OctoPre Dynamicも。
歌撮りと宅録ギターは全て私のRolandのDUO-CAPTURE EX。
マイクプリアンプなんてないし、制作当時はプラグインエフェクトすら持っていなかったので、あとは全てCubase Proの内蔵エフェクト。
モニターヘッドホンは当初はPanasonicの1000円イヤホン笑。
マスタリング作業からはClassic ProのCPH 7000を泣く泣く購入した。
全体的なミキシング/マスタリングのレファレンスとしては、質感の「ヤバさ」は銀杏BOYZやNumber Girlの色々、音圧感はRATMのRenegadesやピノキオPのObscure Question、ドラムのミキシングに関してはTMGEやSOADなんかとも比較しながら作業を進めた。
比較しながら作業をしただけであって、彼らのCDみたいな感じにはあまりできなかったが笑
特筆したいのは、梨本うい氏の「まどのそと」と「手も足も出るのに」だ。サブスクにないので、アルバムデモの動画を貼っておく。
この、巨大な蛇が洞窟でのたうち回っているようなベース、LINE撮りの耳障りな高音域をそのままにミックスされた、ボーカルをかき消す勢いのギター。このバーチャルに再現された四畳半アパートのような非現実的なミキシング…。私の青春時代はこの2枚のアルバムに構成されていたのかもしれない。
ここからは本当の本当に雑記。チラシの裏にでも書けよという内容だ。
前述した通り、レコーディング開始当初は3~4曲入りのデモを予定していた。
From 408のリリース後にアレンジの変わった煙と、収録漏れしていたエネルギー不足を音源化しよう、というのが当初の目標。
フルアルバムを制作してサブスクに流すなんて考えずにレコーディング作業に入った。
From 408はドラムと歌のみ246でセルフレコーディングし、ギターとベースは私の下宿でLINE録音したのだが、私がMarshall 1959を買ったこともあり、今回のレコーディングは全てアンプから撮ってエネルギッシュなものにしよう、という計画であった。
しかしオーバーダブの録音というのはほとほと時間がかかる。
下手に何度でもとりなおせるとなると完璧なテイクを求めてしまう。
しかし私達は完璧なテイクを創造するにはあまりにスキル不足であり、思うようにレコーディングは進まなかった。
そんな折、私のマーシャルが壊れて2ヶ月ほど修理に取られる、メンバーが3週間ほど監禁されるなどの諸事情が重なり、レコーディングはストップ、「このライブまでに仕上げよう」と言っていたライブには到底間に合わないという事態に陥った。
それならいっそ今ある持ち曲を全部音源化してしまおう、という目論見でレコーディングを再開したわけだが、几帳面なオーバーダビング・レコーディングにほとほと嫌気が指したことにより、ドラムトラックの撮り直しのついでで「自己解決」の一曲のみセルフレコーディングでの一発撮りをしてみることにした。
演奏者としても宅録愛好家としても、私自身一発撮りというのは未経験だった。
「試しに録って何とかなったら改めてとりなおそう」くらいの気持ちだったし、ドラムの適当なマルチマイクと、ベーアンとギーアンに至っては適当にSM57を前に置いただけの、レコーディングと呼んで良いのかも分からない至極適当なノリである。
しかしこれが何ともあわせやすく、ストレスも薄く、味のある撮れ方であったため、急遽予定を変更してそれ以降の全ての曲を一発撮りでレコーディングすることとした。
残りの曲は5~6時間ずつ2日に分けて246のセルフレコーディングスタジオを借り、一日目に3曲、2日めに5曲という超ハードワークによって驚異のスピードでレコーディングが進んだ。
というか、本来熱帯夜とクラゲはこのアルバムに入れるつもりではなかったが、2日目のラスト30分間で「折角だから合わせてみるか」というテンションで録った。
そこからはデスクトップPCとモニターを246までせっせとリトルカブで運び、一人で歌を録ってせっせと帰るという地獄のボーカルレコーディングと、一介の素人DTMerには荷が重すぎる生バンド一発撮りミックスとの戦いを2~3ヶ月間続けた。
これについて。
手塚治虫のブラック・ジャックで、開業したての若きブラック・ジャックが重度の白血病(しかも原爆症)患者を診察する回がある。
「できるかぎりのことはやってみた だが なにしろ学校を出たばかりのわたしにとって
相手は原爆というあまりに大きな敵すぎた
それはまるで風車に向かうドン・キホーテのようなものだった(『やり残しの家』より引用)」
以前に数枚宅録でCDを作ったことがあるとは言え、アルバム制作開始時にはモニターヘッドホンすら持っていなかった私が、10曲入りのフルアルバムをミックス&マスタリングするというのは、まさにこのブラック・ジャックの独白そのものであった。(『やり残しの家』はブラック・ジャックの中でも1,2を争う好きな回なのでぜひ読んでほしい)
この回想のコマでは巨大な注射器ひとつを抱えたブラック・ジャックが古ぼけた石造りの風車に立ち向かっているイメージが描かれているが、このコマを私はミックス中何度も思い浮かべた。
ブラック・ジャックは国家試験こそ受けていないがちゃんと(3流の)医大を出ているものの、私はミックスの学校に6年通っていないし、ミックスの基礎すら独学だ。
私が懐に抱えるのはClassic Proのモニターヘッドホンと、DellのデスクトップPC。
2000円の中古モニターの向こうから、ミキシングという巨大な存在が高慢に私を睨みつけていた。
片手に収まるShure SM57が、私には霧のかかった巨大な風車にしか見えなかった。
リリースから半年たった今あらためて聞き返してみたが、なかなかいいミックスだと思う笑
鼻も高くなってきたところで、セルフレコーディングになんの意味があるのか、という話を最後に書こう。
実際のところ、数曲とるくらいならプロに頼んでもそこまで高くない。
はっきり言って安すぎる。
音源制作に必要不可欠な、高価な機材・豊富な知識・潤沢な経験・磨かれた音感・確かなセンス。
世のアマチュア向けレコスタはその、「レコーディング」という5文字半に収めるにはあまりにも巨大な技術を、完全に冒涜した値段設定をつけている。そうはっきり断言できる。
自分で機材を揃える値段も考えれば、アマチュアが軽々しく手を出すには厳しい世界なのだ。これも確かに言えることである。
でも、まともな音源である必要なんかないと思う。
「僕がBig Muffを踏むタイミングで2マスターにディストーションをかけてください」
なんてプロのエンジニアに頼む勇気は私にはない。
それにそんなこと1日や2日では思いつかないし、きっとプロのもとでレコーディングしていたらこのアルバムの半分の曲はボツになっていたと思う。
プロのエンジニアたちには多大なる経緯を払いつつも、私はここに、バンドマンが自力で音源を制作する価値をしっかりと提示していきたい。
ブレイクで無音処理はしない。
マイクの録音ノイズもアンプのノイズもハウリングも切らない。むしろアピールする。
ベーアンをSM58で録る。
シンバルをSM57で録る。
ギターは爆音でミックスする。たまには0dbも割る。
私達のバンドの思想と音楽に掛ける情熱、現代音楽シーンに向けた反骨心を、余すところなく音源に注ぎ込みたい。そのためには、マスタリング段階に至るまで己らで全てを管理する以外の方法は思いつかなかった。
シドヴィシャスはとっくに死んだ。
ジョニーロットンはおじいちゃんになった。
社会不適合者が救いを求めるのは、今やエレキギターではなくヒップホップシーンだ。
こんな時代に許された唯一の反抗が、素人の粗雑なミキシングではなかろうか。
型を知らないと型破りはできない、と人は言う。紛れもない事実だと思う。
だがそんな時間も金もない。
私達の世代が世界を変えよう、なけなしの機材たちを脇にかかえて、音楽業界とかいうあの、古ぼけた風車を取り壊しにかかろう、今すぐに!
2020年10月5日 文責:171 田村晴信