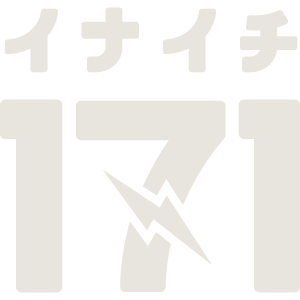2020.10.0517:21
飽き性のあとYouTubeに上げたビデオたち | 171 - Live at 京都GROWLY 2020/10/09
横浜のフェスに出るオーディション(結局最終で落ちた)で、ライブ映像審査があったことと、eo Music Tryの投票促進も兼ねて、10月9日に京都GROWLYで行われた配信ライブの模様を全編まるまるアップロードした。
この日のセットリストは エネルギー不足 / 熱帯夜 / 懐古 / 終演です / 暮らし / みたり
私は個人的にライブ音源・ライブ映像というものがもう大好きで、Bohemian Rhapsodyのベストアクトは結局どのライブなのかとか、SOADのライブは結局初期がいいのか後期がいいのかとか、Sex Pistolsの再結成はアリなのかナシなのかとか、そんなことばかり毎日考えている人間である。
一人のリスナーとしてライブ映像をdigりながらこういうことを考えたとき、いつでも突き当たる問題がある。
「バンド初期が一番パッションがあるのに、売れてない頃の映像と音源はロクなものが残っていない」という話だ。
これはライブ映像に限らずCDのミキシングなんかにも言えることなのだが、要素として感じ取る熱量と、音源や映像としての純粋な聞きやすさ・見やすさというのは、お金の問題で反比例してしまうことが多い。
自分のバンドがこの先熱量を失っていく未来はあまり考えたくないが、「その曲が作られた当時」のライブにしかない熱量が存在するのは確かだろう。
年を取れば考えも変わる。音楽性も変わる。曲に込めたい思いも変わる。
別に初期が至高であるとか、後期は糞だとか、そういう話ではなくて、アプローチが全然変わってくるのだ。
わかりやすく例えを上げるなら、Number Girlの『SHIBUYA ROCK TRANSFORMED 状態』と『OMOIDE IN MY HEAD状態』の違いと言おうか。
オリジナルメンバーの銀杏と、今の峯田と言おうか。
P-MODELの1~2枚目の頃と、後期のライブの違いと言おうか。
System Of A Downの初期と後期もそう。
有名どころなら、Sex Pistolsの現役時代と再結成とか、AC/DCのボン・スコット時代と80年代のブライアンと最近のブライアンとか、Seattle 1989のメタリカと21世紀のメタリカとか。
全然わかり易くない例えで申し訳ない。違法UPの動画もあってすまないが、一応これでも「体裁の整った映像」だけ選んだつもりである。
売れてないバンドのライブ映像なんて、こんな映像やこんなブートレグがあればいいもので、ほとんどはジャリジャリの隠し撮り音声や個人ブログのライブレポートで当時の空気感を想像するくらいしかできないのが関の山だ。
長くなったが、初期の空気感をなるべくダイレクトに知るうえで、後期の味付けの変化を分析するうえで、音質やミックスなんかが障壁になってくるわけだ。
私は自分のバンドでそんなものを許したくないし、その障壁を取り除くためにできる限りのことをしたい。
幸いコロナで今は配信ライブばかりなので、それなりのライブ映像と音声が手に入りやすい。
しかしまあ、どうせ誰も見ない文章なので悪口を書くが、ライブハウスが出す配信映像と音声は、基本客を舐めきった品質のものばかりだ。正直、家で普通に聞いて楽しくはないし、もっとはっきり言うなら金を取っていいクオリティではない。
(その問題を、今回のライブ映像を撮ってくれた京都グローリーさん(以下敬称略)は本当によく考えているようで、映像も音源もハイクオリティだし、いつも注文の多い私達に親身に寄り添ってくれている。)
それをなんとかするのが私の役目。
本当は毎回のライブをMTRで録りたいものだが、最悪LINE録音と映像だけ貰えれば後からゆっくりリマスターできる。
個人的に、そのやり方を解説した自己満足の動画まで制作した。
ちょっとしたコンプとパンニングとルームリバーブをかけるだけで品質が全く別物になることが、いつかライブハウスの皆さんにも伝わるかもしれない。
まあ前述したとおりグローリーの配信は非常に優秀なので、そこまでいじらずに済んでいるのだが。
私はライブ映像オタクだし、音楽オタクだし、宅録愛好家でもあるので、「音楽のかっこよさ」というのは9割ミキシングの品質でできていることを身にしみて実感している。
バンドマンや一部の熱狂的音楽マニアは置いといて、普通のリスナーは低品質ミキシングの音楽を「演奏力のない音楽」と誤認してしまうのだ。
映像に関してもそう、味気ない固定カメラでも、ちょっとした編集で動画としての見やすさや面白さを添加できるのはVulfpeckが証明している。
私は滑舌が悪いが、歌詞字幕を真ん中に付けておけばライブ映像を見ながら自然に歌詞も追えるし。
今回はグローリーの神がかり的映像センスのおかげで無理やり見どころを作る必要もなかったし、30分の映像と音声に対して使えた編集期間が1日という超突貫工事だったので歌詞とタイトルとサムネイル制作くらいの最低限の編集しかしていないが。
といっても、ここまでやってるアマチュアの音楽家というのはまあいない。
この映像を出したライブ審査でも、スマホでライブを撮っただけの映像を出しているバンドばかりだったし。
しかしまぁ、これからの時代、私達も意識を変えないといけないと思う。
インターネットとコロナの時代に、ロックバンドが戦わなければいけないのはライブハウスの対バン相手ではないのだ。
昔のレジェンドミュージシャンでも、レコード会社でも、ヒップホップミュージックでもない。
私達が戦わなければならないのはYouTuberだ。
Roland創業者の故・梯郁太郎氏が生前、シンセサイザー雑誌のコラムに面白いことを書いていた。
「音楽が映像と切り離されて存在するという概念は、レコードという媒体が生み出した幻想だ。レコードが発明されるまで、音楽とは自明にライブであり、映像と一体のものであった。私は自分の会社を使って、音楽をそういう元あった姿に戻したい。」要約すればだいたいこんな感じ。
こと暇つぶしにかけてYouTuberに勝てる音楽家は中々いない。
その点VulfpeckやLouis Cole、ボーカロイド全般を代表とするインターネットミュージックの人々はそこを身にしみて分かっている。
自分たちがYouTubeにPVをアップロードするとき、サブスクで曲を配信するとき、CDを作るとき、私達はもっとYouTuberを意識するべきかもしれない。
極端な話リスナーは、それがYouTuberの動画より面白くないなら、娯楽として選択しないのだ。
ライブそのものもそうだろう。わざわざ金を払って、電車に乗って、ライブを見に行くという行為、これに相当な価値がないと、「家でYouTubeでもみてたほうがいいな」となる。
TV局なんかはYouTuberを舐めていたせいで息も絶え絶えじゃないか。
サブスク時代、曲開始6秒で客を引き込めない音楽は売れなくなっている、なんて言われるが、YouTuberは当たり前に皆そういう世界でやっている。
わざとらしいサムネイルで客を呼び込み、スピード感以外を切り捨てた極端な編集で視聴者を逃さない。
そういう思考で、マーケティングにオールインしているYouTuberやTikTokerたちに、古い感性の我々が勝てるわけがない。
ただし、別にPV自体をYouTuberの動画みたいにする必要はない。
多分YouTuberオタクでも音楽を聴く気分のときはあるだろう、好きなバンドもあるかもしれない。
ましてどこぞの6秒理論に脅かされて、音自体にYouTuber的な詰め込みをしようとかは思わない。
が、動画をYouTubeにアップロードするのであれば、それなりの意識と工夫は必要だ。
その工夫、娯楽のマーケティングと、表現者としてのこだわり、この2つのバランスを常に私達は意識せねばならないと思う。
私は今後、今回のライブ映像以下のクオリティの映像を自分のYouTubeチャンネルにアップロードしたくない。
編集技術も上がってきて、このくらいの映像なら5~6時間で編集できるようになってきた。
字幕、サムネイル、ちょっとした編集、細部へのこだわり。これらと音楽性との掛け合わせをこれからもっと模索したい。もっとインターネットのことを考えたい。
なぜなら私はインターネットで生きてきたから。
インターネットがなかったらとっくに私は自殺していたかもしれない。
虐められっ子だった私に居場所を与えてくれたインターネット、眠れぬ夜を支えてくれたインターネット、思春期の悩みを笑い飛ばしてくれたインターネット、私を堕落させたのもインターネット、責任を押し付けたのもインターネット。
私が思想と情熱をつぎこむバンド活動を、インターネットでやらずに、どこでやるというのだ!!
2020年12月15日 文責:田村晴信