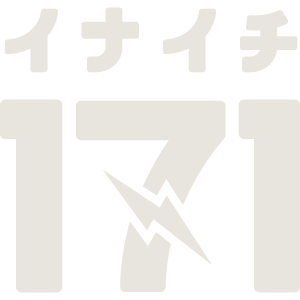2023.07.2519:53
マイ セカンド カー | Internet Killed The Internet Star
作詞/作曲:田村 晴信
編曲:171
物知り顔の知識人達は
しかめっ面で僕らを見て
好き勝手言い合ってた
今や変わりきったこの場所に
あふれんばかりのセンセーション
ロールオーバー・チャックベリー
疑うこともせず
こここそが居場所
21世紀初頭
学校に行けない僕らは
ネット上ひしめきあったろう
今や変わりきったこの場所に
寂し紛れの永遠を
重ねたこともあったろう
時の流れはそれすらも
なかったことにするの?
僕らずいぶん普通に喋って
普通の愛を持ちはじめたね
自分に似合ってる服なんて
いつの間にか見つけちゃって
夕方のワイドショーが
手のひらを返したときには
みんなして大人になっていた
データの海をかき分けて探しても
どこにももう見つからないなんて
今まで気付きもしなかったなんて
もう年寄り気取りの僕たち
苦し紛れ路線変更
夢見た日々も過去の自分も
諸行無常と銘打って
お酒の肴に飲み干した
見たいものだけ見れる世界は
見られないもの消える世界に
美化するほど年老いちゃないけど
忘れ去るほど若くもないかも
何か守るには無力な
僕らとパーソナルコンピュータ
諦めたふりをして
情報化社会のせいにした
"internet killed the internet star"
"internet killed the internet star"
"internet kills the internet star"
"the internet is killing the internet stars"
永遠を願ったこの場所は
移り変わりの象徴に
みんなの悩みに寄り添った果て
この場所も俗っぽさ身につけた
どうしようもない生き物集まって
普通が作られていくのなら
僕もまた普通に生きて
普通に死んでくまでさ
何も変わっちゃいないよ
僕らは元々そんなもの
インターネットのせいにしとけよ
俺ピス→憎まないでと続くインターネット3部作ですから(?)、この曲のギターはすべてPlaytech※のテレキャス(貰い物)でレコーディングした。
※Playtech:音楽系の激安通販サイト「サウンドハウス」のオリジナルブランド。バンドマンはサウンドハウスに足を向けて寝られない
この新品7000円の激安テレキャス、まぁ弾きやすいとは言えないが私好みの音で、今までもかなりレコーディングに使ってきた。
しかしスタジオでアンプに繋いでこのギターを録音するのも、このギターだけで曲を作り上げるのも初めてだったので、なかなかおもしろい体験だった。
この曲のサブタイトルは「ネットスターの悲劇」とします。
私はインターネットの曲を、ご当地ソングの感覚で作りたい。
ので、同じネット観を共有していない人にも聞いてほしい。
よくできたご当地ソングは、その土地で生きる人の生活や感情にフォーカスを当てているので、縁もゆかりもない土地の話でも沁みるものがある。
元ネタにした「ラジオスターの悲劇」もそういう曲だと思う。
ラジオ好きでも世代でもない私だが、ラジオスターの悲劇を聞くと、当時の人々の生活に思いを馳せたり、自分の持つなにかを重ね合わせて感傷に浸ったりできる。
ので。
この曲にはインターネット以外にも色んな、かつての自分の居場所への思いを盛り込んだし、みんなが自分の重ねたいものを重ねてくれたらいいな、と思う。
Video Killed The Radio Starの、いわば「自分バージョン」を作りたいという構想ははるか昔、高校生のときからあった。
当初はもっと替え歌的なノリだったが、今回腰を据えて全編を作ってみて、思ったよりもVideo Killed The Radio Starとは違う角度の曲になった。
出発点としては勿論、Internet Killed The Video Starという曲を作るつもりだったのだが…
正直ヒカキン氏なんかもど直球でビデオスターだと思うし、なにより私はインターネット大好きすぎて、「ラジオスターの悲劇」ほどのテンションでTVを懐かしんで、ネットへの恨み節を歌うことはできなかった。
私たちは全員1997年度生まれだが、我々が中高生で経験したインターネット世界には、ロック黎明期やパンクロック黎明期と重なる、革命の香りが漂っていたように思う。
エレキギターとギターアンプというツールは、ロックミュージックというカルチャーおよび、ロックコンサートという居場所とともに、相互的に発展した。
それと同じように、Digital Audio Workstation(パソコン音楽)と動画サイトと通信速度の発展によって生まれたのがボーカロイド界隈だった。
ボーカロイド界隈とは、音楽の新ジャンルというだけでなく、今までになかった音楽の提供の形であり、今までになかった音楽の聴き方であり、今までになかったコミュニティそのものであった。
70年代にNYやロンドンのグレた若者がロック・クラブに集まってパンクロックが生まれたように、00年代後半〜10年代前半のネットには社会に馴染めない中高生たちが押し寄せ、動画サイトも掲示板も目まぐるしい変化を遂げた。
ボカロの人気動画ランキングは毎日投稿され、当時かなりの数の学生たちが、1日単位1週間単位でシーンの動向をチェックし、新曲を聴いていた。
今考えると物凄いスピード感である。
日本は蚊帳の外?だったパンクロック・ムーヴメントと比べても劣らないほどの熱量が、この国で独自に生まれ、自身がその渦中にいたことを幸せに思う。
その反面、ネットの世界に刹那的な流行り廃りを広めたのも、やはり我々「デジタルネイティブ第一世代」なのかも、という自意識過剰気味な思いもある。
90年代〜00年台前半まで、ネットへのアクセスには専門的な知識と経済力とコンピュータへの愛情が必要だったと思う。
彼らによって形成されていた「玄人のためのインターネット」を、擁護できない若さと親のパソコンで蹂躙し、過去のものとしたのは紛れもなく我々だ。
そしてもう、インターネットの主役は我々ではなくなった。
インターネットの主役などいなくなったといった方が正しい。
ノートパソコンの普及が「玄人のためのインターネット」を「陰キャのためのインターネット」に作り変えたのだとしたら、スマートフォンは「現実とリンクしたインターネット」の発展と共に普及した。
個人情報を公開することへの抵抗は薄まり、我々の世代が物知りおじさん達から奪い取った居場所や価値観は、我々の世代が推し進めた非匿名性によってあっという間に塗り替えられ、時代の先鋒をZ世代に譲ることとなった。
ケータイとパソコンの境界線も曖昧になった。
1人1台、そこらのノーパソより高性能なコンピュータをポッケに入れて持ち歩く時代。
「パーソナルコンピュータ時代」と呼ぶべきだろう。
「ラジオスターの悲劇」で私が1番好きな部分は、Cメロの最後の"Put the blame on VCR"という歌詞だ。
「ビデオデッキのせいにしよう」とでも訳しておく。
「ラジオスターを殺したのはビデオでもTVでもなく、ラジオを聞かなくなった自分たち自身」という裏テーマを暗に示す一文だと私は解釈している。
それこそを表のテーマとした曲を作りたかった。
2023年7月25日 タムラ