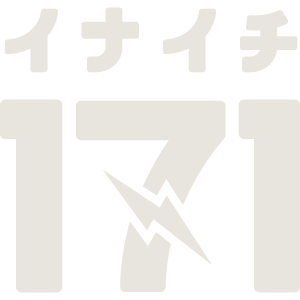2025.01.1611:57
Life Size Life | ヒットソングシーズン
作詞作曲:田村 晴信 / 編曲:171
永遠なんて望まなければ
僕らまだそばにいれたかな
出会ったころの写真を見ても
同じ結末が浮かぶな
完璧なんて望まなければ
僕らまだそばにいれたかな
笑って写る写真を見ても
思い出すのは やなことばかり
心ない言葉と人は言うけれど
心がなかったら
言わずにすんだ言葉でしょう?
それとも言えずに終わった言葉を
腐らせるために
僕らに心はついていたのか
僕らの過ごした 遥か道のりの彼方
互いの心 覗き飽きてしまった
必死の思いで 飲み込んだ言葉も
息遣いひとつで わかってしまった
知ってる景色が
ちらほら流れて
このドライブもそろそろ終わり
優しさの材料を(見飽きた街に)
生活が食い潰して(吸い込まれたら)
残高の優しさは(明日からまたいつもの暮らし)
押しつけがましく見えた
さよなら僕らのちっぽけな
もう戻れない暮らし
あの曲を いま聞いてる
僕らの過ごした 遥か道のりの彼方
いつの間にやら 疲れ果ててしまった
巷にありふれた あんなヒットソングが
僕だけのために 歌いはじめた
この曲についての話は、長くなってしまう。ごめんなさい。
●CASANOVA FISHと秋音。とNUMBER GIRLについて
歌詞とメロディは「マイセカンドカー」リリース直後から考えていて、どんなアレンジをつけるかで非常に悩んでいた。
CASANOVA FISHという東京のバンドが2023年に、出身地である長野県伊那市(「いなし 」←イナイチとも読める❗️)のグラムハウスというライブハウスに呼んでくれた。
「AFTER SCHOOL SUSTAIN」のリリース記念だったと記憶しているが、そのEPには「SEVENTEEN BOY'S BLUE」と「ROOFTOP FAN CLUB」という曲が入っている。
タイトルを見ただけでニヤけてしまう。
どう考えてもナンバガの「YOUNG GIRL SEVENTEEN SEXUALLY KNOWING」と「IGGY POP FAN CLUB」である。
「俺もそれやりたい!」と思いたち、関西に帰ってすぐにこの曲のリフを作った。
のだけれど、「Number Girlってわかるリフだけど、完全パクリじゃないギリギリのライン」に集中して作りすぎて、逆にCASANOVA FISHの「SEVENTEEN BOY'S BLUE」とほぼ同じリフになってしまった笑
どうしたものかとキーを1個さげたり、4カポにしたりして、レコーディングまでにはなんとかモロパクリラインからはギリギリ逃れたリフに仕立てた…はず。
アウトロに入っているブレイクは、その日の1番手で出ていた「秋音。」という地元長野のバンドがやってた曲をめっちゃ意識した。
秋音。のブレイクはもっとかっこよかった笑
ヒットソングシーズンでは今ひとつになってしまったが…。これで秋音。よりかっこよかったらもう完全にタチの悪いパクリだったので、これで良かった気もする…。
「あの曲を いま聞いてる」の1文はもちろん、Number GirlのIGGY POP FAN CLUBから。
「確信犯(誤用)Number Girlですよ」という宣言のつもりで入れた。
●バラードについて
中学生のころ、バラードが本当に嫌いだった。
中学はるぽん(私:タムラハルノブのことである)は「俺はこのまま誰とも恋仲になることなく童貞のまま死ぬんだ」と悲観に暮れていた。
世間で「歌詞がいい」って言われているバラードは、もう本当にラブソングば~~~っかりで、中学はるぽんはそれにキレまくっていた。
私は郷愁とか哀愁とか懐かしさとか、そういう出どころのわからない寂しさとかしがらみみたいなものに人一倍敏感なガキだった。
小学はるぽんのころは、CDプライヤーにヘッドホンを繋いで「モルダウ」を聴きながら、存在しないモルダウ川への郷愁にかられて一人居間で涙を流していた記憶がある。
ガキポン(ガキはるぽんの略)がバラードに求めているものはそういう、心の奥底から理由もなく湧き出てくる寂しさ、時の移ろいに対する免疫反応、そういったものだったのに、世の中のさみしい曲って基本的に「恋人との別れ」という共通体験をドレスコードとして成立していた。
ガキポンは当時、「『残り香』とか言われても、残り香知らんねん!」という名言を残している。
ラブソングであふれる巷のヒットチャートは「陳腐でありふれたくだらないもの」としてガキポンの目に写った。
今から思うと、こういう鬱屈した感情がガキポンをロックシーンやボーカロイドシーンへと導いたのだと思うし、このEPの一曲目をEIGHT BEAT SEASONにして本当によかった。
そうやって恨んでいた曲たちをオトポン(大人はるぽん)になって聞き返して、まんまとオトポンはラブソングの虜になってしまった。
プリプリの「M」、中島みゆきの「わかれうた」、西岡恭蔵の「プカプカ」、ばちかぶりの「オンリー・ユー」、ピノキオピーの「ラブソングを殺さないで」、「真夏の果実」や「波乗りジョニー」、クリトリック・リスの「その時、俺は」、モールルの「サイケな恋人」、ピストルズVerの「No Fun」、Theo Katzmanの「The Death of Us」、The Arrogant Sons of Bitchesの「Piss Off」、Jeff Rosenstockの「Twinkle」、the coopeezの「無力な瞬間」、サンボマスターやNumber Girlや銀杏BOYZのすべて。
世の中のラブソングは、恋愛を歌っているんじゃなくて、人との出会い、人との別れ、普遍的なそのものを歌っている。
私もそういうつもりで曲を作っている。
自分はラブソングしか作っていないとも思っているし、ラブソングなんて1曲も書いていないとも思っている。
大変遺憾ではありますが、ガキポンをはじめとして多くの人間は、ある程度の恋愛経験を経るまでそのことに気付けない。
なんなら、世間から「ラブソング」と思われている曲の中には、「音楽で夢を追ったことがある」という経験が裏ドレスコードになっている曲も密かに存在している。
憂歌団の「嫌んなった」とか、相対性理論の「バーモント・キス」なんかはそうだと信じている。
台風クラブの「火の玉ロック」とかPUPの「If This Tour Doesn’t Kill You, I Will」なんかは間違いないけれど。
この曲で「ヒットソング」と呼んでいる曲を列挙していったらきりがない。
「別れ」という巨大な存在に一矢報いるため、古今東西たくさんのミュージシャンが思い思いに歌詞をしたためてきた。
玉石混交のラブソングたちの屍の山、光り輝くヒットチャート。
そんな中で、私が最も特別な思いをもっているのが杏里の「オリビアを聴きながら」でありまして。
●『オリビアを聴きながら』について
私の祖父は昭和7年生まれで、今年93歳になる。
流石に病気がちにはなったけれども、昭和1桁世代のパワーを未だに感じる。
元祖・昭和の雷親父であった。
私の故郷は京都、紙屋川(もう少し下流では天神川と呼ばれる)のほとり。
西陣織のジャガード機のバッタンバッタンという音が1日中鳴り響く、少々やかましい町だった。
祖母は二条あたりの出身で、「新婚の頃は、西陣織の機械がうるさくて眠れへんかった。でもこの家の人は、生まれたての赤ちゃんまでみんな、ぐっすり寝てるから不思議やった。」なんてことをよく言っていた。
うちの家族は朝に弱い。
目覚まし時計が鳴り響いてもぐっすり眠れてしまうのである。
このへんの人らはみな朝弱いはずや、と母は言っていたが、多分そんなことはない。
私の育った小学校は来年春に廃校になる。
実際、私の入学時には全校生徒120人いたのだが、卒業するときには既に100人を切っていた。
もちろん1学年あたり1クラス。
卒業時、1学年あたり20人以上いたのは私の学年だけだった。
中学に上がるまで私達は、漫画やドラマに出てくる「クラス替え」という行事を体験したことがなかった。
12人しかいなかった学年では給食当番に必要な最低人数を割っていたため、彼らは6年間すべての週で給食当番だったし、日直も週一で回ってきたらしい。
山間部とかいうわけでもなくタダの住宅街なのだが、かつては極端な人口密集地だったために近隣の小学校から独立したらしく、とても校区が小さかった。
「こどもだけで校区から出てはいけません」という校則があったが、うちの生徒がこれを守ることはまるで不可能だった。
みんなで集まる駄菓子屋も公園もスーパーもコンビニも校区外にあるし、校区外の道を経由しないと登校ができない生徒まで存在した。
うちの家からも車で送ってもらうと、一方通行の兼ね合いで2~3個の別の小学校区を経由して行くことになる。
もっと早くになくなってもおかしくないチンケな小学校だったが、隣の小学校が既にマンモス校だったり、別の行政区だったり、いろんな事情で陸の孤島と化していた。
はっきり言って、差別から生まれた事情もあった。被害者側としても、加害者側としても。
私の祖父はそんな京都市立柏野小学校の、記念すべき第1期1年生だった。
(もう特定できる材料が揃ってそうなので言っちゃいましたが、いくら小さい校区とはいえ「田村さん」は1軒だけじゃないので、僕の実家を探そうとしないでください…。)
当時は第四待鳳(たいほう)尋常小学校という名前だったそう。時代を感じる。
施設の建築が間に合わず、待鳳小だったか紫竹小だったかの講堂で入学式を行ったと伝え聞いている。
祖父は、母校の始まりから終わりまでを見届けたことになる。
そんな我らが柏野学区80年の歴史上、一番の有名人が歌手の尾崎亜美さんだ。
何を隠そう、「オリビアを聴きながら」の作詞作曲を担当されたミュージシャン。
親と世代が近いこともあって昔から自慢話は聴いていたが、カラオケで友人が「オリビアを聴きながら」を歌っているのを聴いて、ポップシーンのど真ん中にこんなにも踏み込んだラブソングがあったのか、と衝撃を受けた。
今僕は柏野に住んでいない。
けど小学校のころは、自分は柏野で生きて、柏野で子どもを育てて、柏野で死ぬんだと思っていた。
それが「正規ルート」だと思っていた。
姉も友達もみんな、一生柏野を出ないでほしいと切に願いながら、モルダウを聴いていた。
いざ廃校が決まってようやく気付いたが、小学校の本質は校舎ではなくて、校区なんだろう。
校舎が残っても「柏野」を冠した町名が残っても、「こっからここまでの人は柏野の人ですよ」という決まり事は消えてなくなる。
本当は、そんなものはただの行政区画に過ぎない。
自分とか他人とかを、戦前のお役所が決めた区画に縛られて捉える必要なんかこれっぽっちもない。
でも柏野学区の85年は、激動の昭和から令和までをかけて、私の祖父の一生涯をかけて、単なる行政区画に行政区画以上の意味を育んだ。
自分の出身を聞かれて、「柏野」と答える子どもがこの世からいなくなるということは、正直言って凄くさみしい。
でも不要なしがらみを次世代の子どもたちに残したくない。
きっと今までもたくさんのしがらみを、たくさんの世代の親が飲み込んで飲み込んで、僕は不当にすくすくと育つことができたと思う。
こうなった以上、カテゴリとしての柏野なんてものは、一刻もはやく人々の脳裏から消え去るべきかもしれない。
横の翔鸞(しょうらん)小学校に吸収される形となるから、在校生は大変な思いもするとは思う…。
来年からの新入生は「翔鸞学区生」として入学することになるが、10年くらいは「元柏野」というまったくもって不要なしがらみを背負わされるかもしれない。
でも僕にはそれを否定できない。
このジレンマを慰める唯一の方法が「オリビアを聴きながら」なのかもしれないなと思った。
ちょっとおかしな町で育った先輩が、世界中どこにでもある陳腐でありふれたくだらない平凡な別れを、非凡な才能でまとめあげた曲。
僕にとって、ヒットチャートの頂点のひとつとも思えるほどの1曲。
柏野というしがらみが存在した証拠は、この1曲だけで十分なんじゃないかと思った。
ヒットソングシーズンの歌詞を書くにあたって、「あなた」とか「2人」とか「恋」とか、恋人との別れをドレスコードにしてしまうワードを入れないように細心の注意を払った。(こういうこだわりはピノキオピーから教わったと思っている)
でもきっと当時の自分がヒットソングシーズンを聴いたら、唾を吐くだろうとは思う。
ラブソングは絶対に誰かを傷つける。その事実から逃げるんじゃなく、その事実と向き合っていたい。
子どもの頃の自分に「オリビアを聴きながら」を聴いてほしくてヒットソングシーズンを作ったんだなと、今気付いた。
2025/1/16
文責:タムラ